マウントしているディスクについては df -Tで確認できるけど
マウントされていないディスクについて確認するのが困った。
parted -lで対象のディスクを見る方法もあるが、
blkidコマンドで確認しやすいと思う。
blkid 対象のディスク
例root@vds05:~# blkid /dev/sda1
/dev/sda1: UUID="a3867239-aa78-4444-8fa2-e64c90c25898" TYPE="ext2"
ネームサーバーの概念
今まで自分はネームサーバーの存在意義についてよくわからなかった。
ネームサーバーとは一般的にDNSのことを指し、DNSとはドメインとIPを結び付けるものといわれている。
なので、DNSとは、ドメイン=IPだと思っていて、Aレコード=DNSと考えていたからだ。
もちろんドメインの使い道はwebサーバーだけじゃないのはわかってたけど。
ネームサーバーはどちらかというと、対象のドメインのレコードを知るための手がかりで、
その手掛かりとしてIPを利用していると思うようにする。
つまりネームサーバーに利用するIPは対象のドメインの各レコードの情報知るための住所。
ややこしいところとしては、各レコードのIPを知りたいのに、それを知る手段がIPだということ。
仮にDNSがIPとかじゃなくて、DPとか違う言い方だったら悩まずに済んだかもしれない。
PacketiX VPN の概念
PacletiXVPNを利用すれば、レイヤー2でVPNを構築するためプロトコルを気にせずに通信ができるそう。
例えば、ポート25が閉じられていて対象のリモートサーバーにメールを飛ばせない時は、
ポート443からメールを飛ばせるようなことができる。
PacletiXVPNはGUI上で操作できるため初心者でも容易だそうな。
なおVPNはトンネリングと暗号化で成り立っており、トンネリングは、
パケットAでしか通せない情報をパケットBも通すためにカプセル化すること。
暗号化はパケット内の情報を第三者にみせないこと。
カプセル化ってものをいつかやってみたい。
lxcで空のディレクトリを作るとき
lxc-start -d -n <<vmname>> でエラーが発生することがあった。 気になるところは、 /var/lib/lxc/vmtest/rootfs をマウントすると出来ないが、 マウントを外すとアタッチすることができた。 どうやら、マウントをする前にlxcをクリエイトしてしまったことが問題だった。 つまり、論理ボリューム上ではなく、サーバーのホスト内にlxcを作成してしまったため、 マウント後の /var/lib/lxc/vmtest/rootfs のディレクトリ以下は何も作成されていない状態であった。 もちろんマウントを外すと上記のディレクトリ以下にはファイルがあるためlxcがスタートできる。 なので、論理ボリューム上にlxcを作成したいなら先にマウント先のディレクトリを作ろう
肌色の練習(※18禁)
恥じらいがあったものの塗ってみるとだんだん立体的になるので面白い!
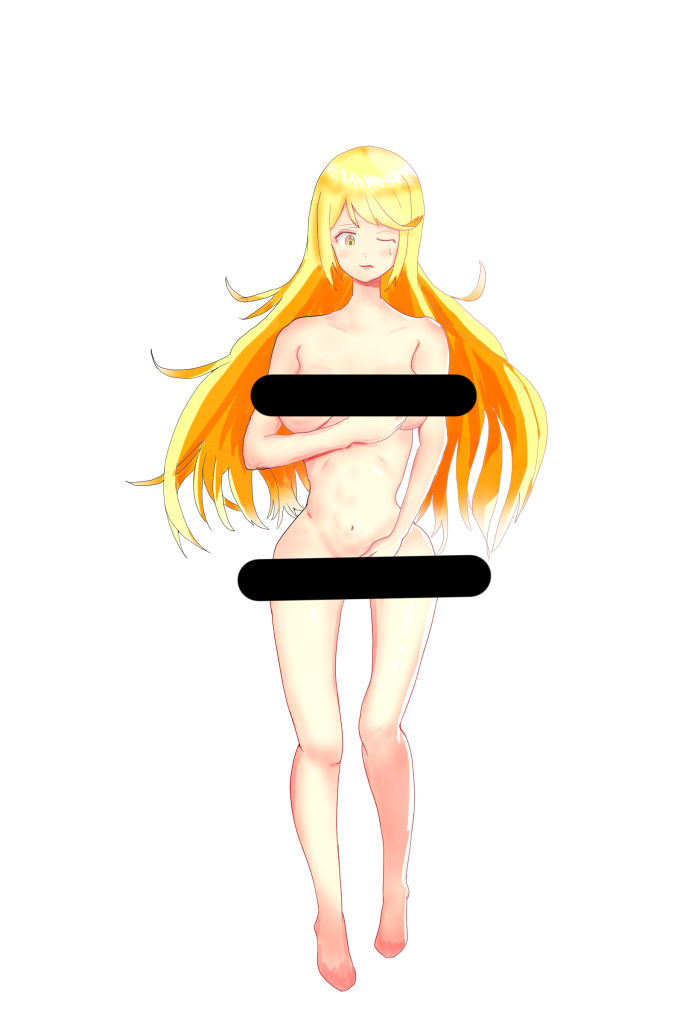
もう少し明暗はっきりしてもよかった?
内容は初めてのあれみたいな感じ
linuxでOSを確認する
自分が利用しているサーバーのOSがCentOSとかubuntuとか確認したい場合がある。
これまでは下記コマンドでCentOSかubuntuかを確認していた。
CentOSの場合なら下記ファイルが存在するかしないとか
cat /etc/redhat-release
ubuntuの場合なら cat /etc/os-release
改めてググってみると下記コマンドでよかったcat /etc/issue
ただし、/etc/issueってログイン前のメッセージを表示するらしいので、
場合によっては表示されない可能性あり
ついついツインテール

今回だけは許してあげなくもないんだからね。
ツインテールといえばツンデレとか勝気ってイメージが自分のなかであります。
最近、しっかり絵を完成させることより継続することのほうが大事だからラフでも描きたいものをかくことにした。
本当は成長を妨げるんだけど、今まで一度書いたら完成させるまでアウトプットできないってのがつらかったから。まずは楽しむことを優先とした
Elastic Cacheでスケーラブル
インスタンスをスケールアウトするためにはステートレスでなければいけない。そのためにElastic Cacheにデータを一時的に保持しておく。
ステートレスとは外部からの情報のみによって出力がきまるもの。
ステートフルだとサーバーが既に保持している情報によって障害が発生するようだ。
なんだろう、オシャレ

一時創作して遊んでいたんだけど、レイヤーの基本的な部分を抜いてみたところふわっとオシャレになっていた。
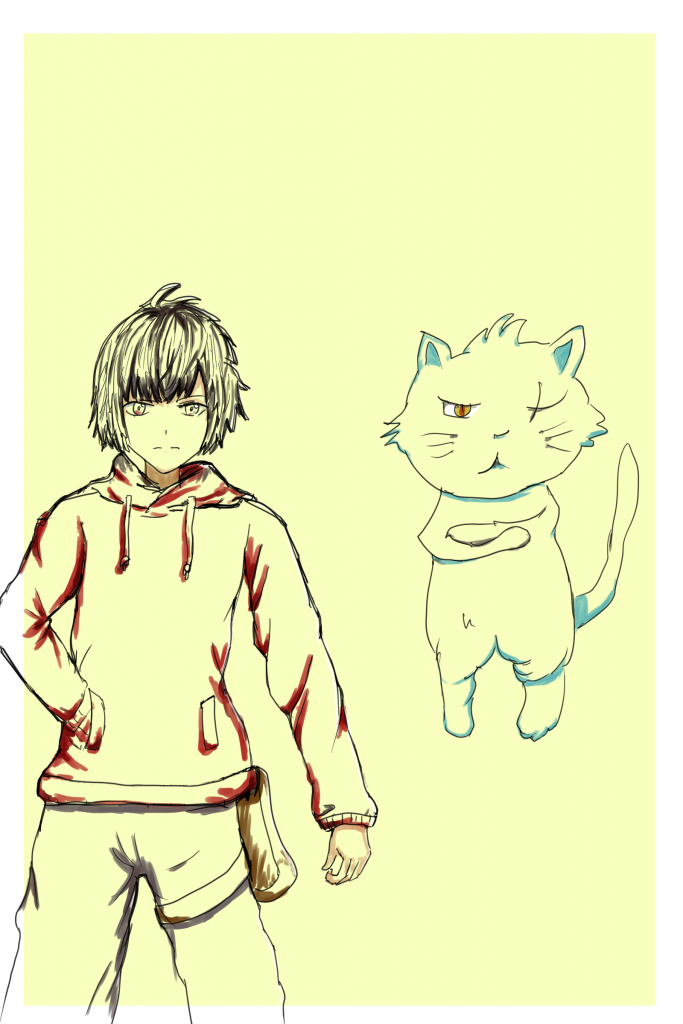
なんだろう、黄色とベースとした統一感がいいのか。影が際立って立体感を見てる側の脳で保管してしまうからなのか。不思議な発見
NATからGatewayへの考え方
AWS上でルートテーブル上でローカルIPからNATを通した機器とインターネットゲートウェイに繋がる機器を作成したときに思ったこと。
NATを通す機器に対してなぜローカルIPを割り当てる必要があるか理解ができていなかった。
もっといえば、グローバルIPがあるのになぜローカルIPもついているのも理解できていなかった。
結局、NATが付いたローカルIPも機器だから当たり前なんだよね。その機器もネットが必要だから。
だからルーターとかもローカルIPが割り当てられていると思う。


